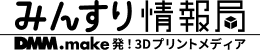2023年6月注目の3Dプリンター/AM関連ニュースをお届けします。
新技術や素材の開発からより便利になる新サービスまで、国内外でおこった革新的な5つのトピックをDMM.make が独自の視点で厳選してご紹介。
3Dプリントの可能性に触れてみましょう!
StratasysとDesktop Metalが合併、3Dプリント業界に大きな動き
5月末から3Dプリント業界に大きな動きが見られました。
大手3DプリンターメーカーであるStratasys社と金属3Dプリンターに強みをもつDesktop Metal社が合併を発表しました。両社の技術が融合することで、製造業やものづくりのさらなる発展が期待されます。
一方で、6月頭には3D SystemsからStratasys社へ買収の提示があり、3Dプリント業界で大きな再編がありそうです。
参考:ロイター「3Dシステムズ、ストラタシスに12.1億ドルで非友好的買収提示」
3Dプリンター技術で復興の一翼を担う、ウクライナの学校建設
3Dプリントの力が社会貢献にも活用されています。
ウクライナの復興支援のため、フューチャリストで起業家のジャンクリストフ・ボニスとデジタル建設の専門家ドミニク・ピヨテがリーダーシップを執り、3Dプリンター技術を活用した学校の建設を開始しました。
世界最大の3Dプリンター製の平屋校舎で、3Dプリンターで教育施設が建設されるのは、ヨーロッパ初となります。
このプロジェクトには建設3DプリンターメーカーのCOBOD社のコンクリートの3Dプリンターが用いられました。
従来の建設方法よりも時間とコストを大幅に削減できる点も注目を浴びています。3D プリント コンクリートの材料の99% は地元で低コストで調達され、総床面積 370 平方メートルの平屋建ての建物の半分がわずか3~4日でプリントされました。
参考:Forbes JAPAN「世界最大の「3Dプリント」製校舎の建設進む、ウクライナ復興支援で」
COBOD International「Rebuilding Ukraine with a 3D Printed School」
スワニーと3D Systems、大型部品のペレット3Dプリンティングで協業

長野県に本社をおく有限会社スワニーが、3D Systems社と協業し、大型部品のペレット3Dプリンターの開発を進めます。この秋には「EXT 1070 Titan Pellet」を備えたデモセンターを開設する計画です。
「EXT 1070 Titan Pellet」は、射出成形などに使う市販の樹脂ペレットを使って造形できる押し出し方式の3Dプリンター。最大造形サイズは幅1060×奥行き1060×高さ1210mmで、市販の樹脂ペレットを使用できます。
さらに、リサイクルペレット材料も使用できることを目指し、サステナブルなものづくりへの挑戦に意欲を見せています。
「日本の企業・技術が世界的メーカーから注目され、手を組んだ」という事実に胸が熱くなりますね…!
参考:
日経クロステック「スワニーと3D Systems、大型部品のペレット3Dプリンティングで協業」
株式会社スリーディー・システムズ・ジャパン「3D Systems とスワニー、大型ペレット押出3D プリンティングの普及に向けて協業を開始」(プレスリリース)
ものづくりワールド/次世代3Dプリンタ展開催
これまでも度々こちらで取り上げてきた「ものづくりワールド」および「第6回 次世代 3Dプリンタ展」が開催されました。出展社数は1,750社、来場者数は66,895人にのぼったと発表がありました。
3日間の様子はぜひ以下のレポートからもご覧ください。
DMM.makeがMJFホワイトをアジア初導入、エンジニアリング素材取扱い開始など素材数が56種へ
DMM.makeとしてのビッグニュースは取扱い素材数の拡充です。
アジア・オセアニア地域初導入を実現した「PA12W ホワイト | MJF」の取扱いを先月5月に開始、そして6月28日にはエンジニアリングプラスチック素材を含む16種のハイエンド素材をリリースいたしました。
これにより、DMM.makeでの取扱い素材は2023年6月現在56種類へと大幅に増加しました!
3Dプリント外注サービスでは国内最大規模の取扱い種類です。
法人のお客様に限らず個人やクリエイターの皆様が、1品、1パーツからでも気軽にハイエンドな素材をご注文いただけるのもDMM.makeならではの魅力です。
「このような用途で使いたいのだけど、どの素材を選べば良いか分からない」といったご相談も、お気軽にどうぞ!
エンジニアリングプラスチック含む17種類を取り扱い開始!最高レベルの耐熱性や耐薬品性が叶う製品をDMM.makeの3Dプリントで
編集後記
3Dプリント/AM業界を取り巻く環境は著しく変化しています。
これからも世界の動向に目を向けつつ、ものづくりに向き合い、楽しむ方々にとってタメになる情報を発信できたらと思います。
ちなみに、編集部のプチニュースとしては翻訳記事の配信を開始したことでした!
2023年は日本での「3Dプリントブーム」そしてDMM.make 3Dプリントサービス開始から10年目と節目の年になります。
一体これからの10年はどんなことが起こるのでしょうか?
これからもDMM.makeと一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。